
節分といえば、思い浮かぶのは豆まきに、恵方巻。
毎年年明けから、恵方巻の予約の受付が始まるなど、節分に恵方巻を食べるものだというのは、現在では全国に広がっている風習でもあります。
しかしながら「恵方巻」として全国的に知られるようになったのは、意外と最近の話なのです。
恵方巻について、ルーツやお作法などを詳しく知っている人は、まだまだ少ないといえますので、ここでご紹介していきます。
節分だからなんとなく食べている人も多い、恵方巻。
本当の恵方巻というものを知って、正しいお作法でいただき、ご利益をいただきましょう。
目次
今年2025年の節分は何故2日2日?ずれる原因は?次はいつ?
今年2025年の節分は何故2日2日?ずれる原因は?

「毎年、節分は2月3日なのにどうして2025年は2月2日なのだろう」と疑問を抱いている方が少なくありません。
これはうるう年が関係しています。
うるう年の次の年の節分は2月2日になるのです。
太陽の好転周期は365日ぴったりではなく、そのズレを調整するための4年に1度、2月29日があります。
そのズレの修正によって立春の日付が前後することから節分の日も変わるのです。
ちなみに、2024年がうるう年でした。
2月2日の節分は次はいつ?過去に2月4日の節分はいつだった?今後の節分がずれる年はいつ?

うるう年の次の年の節分の日付が2日になりますから、もちろん過去にも未来にも起こります。
2025年の一つ前は2021年ですし、一つ先は2029年となります。
しばらくは4年に1度で2月2日となりますが、2057年、2058年だけは連続となるようです。
節分の本当の意味とは?

「季節を分ける」ということで節分といいます。
節分は古代中国からの由来があり、宮中での「追儺(ついな)」という鬼祓いの儀式が民にも広がりました。
節分を迎えることで季節の変わり目に、漂う邪気を祓う風習があったのです。
邪気を祓うことでこれからの一年の幸せを祈願することに繋がるのが本当の意味だといえます。
豆まきの由来や意味

宮中で行われていた「追儺(ついな)」と合わさって豆まきが始まったといわれています。
そもそも、五穀に鬼を祓う力があると信じられていたので、豆まきによって鬼を祓っているのです。
豆は「魔滅」と書いてまめとも読み、無病息災を祈る意味もあり、節分による豆まきはこれからの一年の幸せ祈願にも繋がります。
豆まきにはやり方があります。
豆まきを行うのは夜で、家族が全て揃ってからとします。
玄関から最も遠い部屋から豆まきを始め、鬼を追い出しきるためにも玄関まで行います。
鬼に向かって豆を投げるだけでなく、「福は内」と室内に向かって投げて拾って食べます。
ただし、やり方は地方によって異なる場合がありますので、気になる方は調べてみてください。
恵方巻の由来や意味(昔は無かった?下品な由来って?いつから流行った?)

実は節分に恵方巻を食べるのは昔は無かったものです。
江戸時代から明治時代頃に恵方巻を食べる習慣が始まったようで、商売繁盛や無病息災を願う方が行っていました。
実際に「恵方巻」と呼ばれるようになったのは1980年代で、それまでは「丸かぶり寿司」「太巻き寿司」という呼び名でした。
由来は諸説あります。
縁起を担いで恵方に向かって食べたのは大阪の花街だといわれていますし、コンビニが「恵方巻」と名付けて売り出したのが最初という話もあります。
いつから流行ったのかは、昨今のスーパーやデパートなどの販売によるものだといえます。
「恵方巻の下品な由来がある」と噂されているのは、由来の中に、花街や船場の色街というワードが出てくるからかもしれません。
恵方巻をいただくことに下品な意味はないので安心して楽しんでください。
2025年恵方巻は2月2日に食べるのが吉
恵方巻とは、節分に食べる縁起物

「恵方巻」というのは、節分の日にその年の恵方に向かって、黙って食べる長い一本の太巻きのことを言います。
太巻きは、巻き寿司の一種で、海苔巻きとも呼ばれますが、具が多く、太さがあるものを総称して太巻きと呼んでいるのです。
これに対して、細く長いものは細巻きと呼ばれていて、鉄火巻きやかっぱ巻きといったものが細巻きに当たります。
恵方巻は、七福神にちなんでいるとされていますので、7種類の具を入れたものがオーソドックスな恵方巻とされているのです。
恵方巻を食べる時、黙って願い事をしながら、切らずに丸かぶりして食べることで、願いが叶う・厄除けになるといわれています。
ルーツは、関西・大阪にあるといわれていて、次第に全国に広がっていったのです。
このことから恵方巻は、節分に食べる縁起物とされているといえます。
恵方巻を食べるのは節分の日で、2025年は2月2日

恵方巻は、節分に食べるものです。
節分というのは、二十四節気の一番初めの節気である「立春」の前日のこと。
冬が終わり春へと移り変わっていく、季節の分かれ目となる日です。
節分は、毎年2月3日だと思っている人がほとんどですが、実は2月3日ではない年もあります。
2021年の節分は、節分が2月2日だということが話題になったことも、記憶に新しいものです。
ちなみに節分が2月3日ではなかったのは、2021年の前でいうと37年前の1984年で、2月4日でした。
前回2月2日が節分だったのは、1897年と、なんと125年も前のこと。
このように不定期に変動している節分の日ですが、次に節分が2月3日ではない日は、2025年の2月2日です。
なぜこのようなことが起こるのかというと、立春の日が変わるにつれて、節分の日も変わることになるから、というのが理由。
地球が太陽を一周することで、一年が経ちます。
一年は365日とされていますが、厳密にいうと、365.2422日なのです。
何年も積み重ねていくごとに、この0.2422日の差はどんどん開いていってしまいますので、4年に一度うるう年を設定することで、そのズレを調整しています。
ところがうるう年を設けることで、調整しきれない微妙なズレが生じてしまうのです。
この小さな小さな誤差を調整するために、立春の日が不定期に変化することになり、節分の日にも変化があるということ。
2025年の節分は、2月2日になります。
恵方巻の歴史の始まりは諸説あり

節分に恵方巻を食べるようになった歴史については、諸説あって、どれが正しいものかハッキリしていません。
その一つは、江戸時代から明治時代にかけて、大阪の芸子さん・商人たちが花街で、「商売繁盛」や「無病息災」を願って恵方巻を食べたのが始まりだとされている説です。
この時には恵方巻という名前で呼ばれておらず、「太巻き寿司」や「丸かぶり寿司」と呼ばれていましたが、一気に食べ進めるという点では、すでに現在の恵方巻のスタイルに近いものが出来上がっていました。
もともと関西には、その年の恵方にある寺社に参拝するという「恵方詣り」の風習があり、このことが恵方巻と結びついて、恵方を向いて丸かぶりをするという恵方巻の習慣が始まったのではないかとされているのです。
時代がもう少しさかのぼって、戦国時代だという説もあります。
戦に出陣する前に、節分に太巻きのようなものを食べて出陣した際、大きな勝利を収めたことから、それ以後太巻きを縁起の良いものとして考えるようになったことが、恵方巻の始まりではないかといわれているのです。
その後、コンビニエンスストアやスーパーなどが、節分の商戦として恵方巻を販売したことから、全国に広まっていったとされています。
恵方巻が広まったのは、海苔屋さんとお寿司屋さん、そしてコンビニエンスストアがキッカケ

恵方巻のルーツはハッキリしていませんが、大阪の商人や芸子さんたちが「商売繁盛」を願って始めたというのが、最も有力だといわれており、実際大阪では恵方巻を食べていた風習がありました。
昭和時代、そんな大阪の風習に目を付けたのが、大阪の海苔屋さんとお寿司屋さん。
恵方巻の原型でもある太巻き、恵方巻の材料となる海苔を売るための商戦として、「幸運巻き寿司として、節分には丸かぶり」というチラシを配ったのです。
これが、恵方巻を広げていったキッカケになったとされていて、丸かぶりするという食べ方の由来にもなっているといわれています。
恵方巻を広げていったのは、海苔屋さんとお寿司屋さんだけではありません。
その大きな役割を買っているのは、実はコンビニエンスストアなのです。
そもそも「恵方巻」という名前を付けて発売したのは、あのセブンイレブンが最初だとされています。
大阪での風習を季節の行事として考え、1989年の節分に合わせて、広島県の一部の店舗で発売したのが始まり。
1月2月のコンビニエンスストアの売り上げが落ち込む時期、売り上げを少しでも上げようとする商戦の一つだったのです。
セブンイレブンが発売して以降、ほかのコンビニエンスストアでも、「太巻き」「丸かぶり寿司」「節分の巻きずし」などさまざまな名前で売り出していたのですが、1998年にセブンイレブンが「恵方巻」と銘打って売り始めてからは、「節分には恵方巻」と全国に広がっていったということ。
今では毎年コンビニやスーパーで当たり前のように売られている恵方巻ですが、全国的に恵方巻が主流になったのは、意外と最近でまだ歴史は浅いものなのです。
北野天満宮では1月25日の初天神の日、恵方巻用の海苔が無料配布される
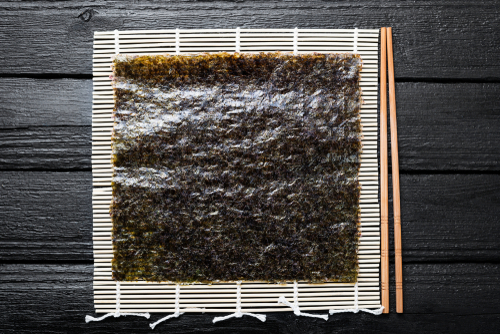
北野天満宮では2005年から毎年、恵方巻用の焼き海苔を無料で配布しています。
海苔の消費の拡大をアピールするためとして始まった、この無料海苔の配布ですが、11時から配布が開始されるとあって、配布前から長い列が出来ているのです。
北野天満宮で配布される海苔には、「ご利益がある」「福を呼ぶ海苔」といわれていて、多くの人が福にあやかろうと、並んでいます。
海苔が配布されるのは、初天神の日である、1月25日。
北野天満宮に祀られている菅原道真公の、誕生日が6月25日、没日が2月25日であることから、毎月25日は縁日が行われていて、たくさんの露店も出ています。
一年の始めである1月25日に行われる縁日を初天神といって、受験シーズン真っただ中ということもあり、合格祈願に訪れる受験生やその家族、梅の花を見物に来る人など、露店が出ているだけではなく、参拝客などでとてもにぎわっている日なのです。
海苔の無料配布は、無くなり次第終了となっていますので、早めに並んでおくことをおすすめします。
2025年の恵方は西南西が吉!
恵方というのは、その年に歳徳神(としとくじん)がいる方角のこと

節分によく聞く、恵方巻の名前にもなっている「恵方」というのは、ひと言で言えば、その年の運気が良いとされている方角のことをいいます。
その年の福を司る神様である、「歳徳神(としとくじん)」がいる方向です。
お正月に迎える年神様(歳神様)と同じ神様のことで、昔は初詣も恵方にあるお寺にお参りをする恵方詣りをしていました。
恵方を決めるのは、その年の十干(じっかん)によって決まるのですが、もっと簡単に見分ける方法があります。
それはその年を西暦で表記した時の、下一桁の数字で見る、という方法。
下一桁が、4・9の年は、恵方は「東北東」になり、0・5の年には「西南西」、1・3・6・8の年には「南南東」、2・7の年には「北北西」になるのです。
ちなみに十干(じっかん)というのは、例えば2022年でいうと、「壬寅(みずのえとら)」となるのですが、この「寅」は十二支でなじみがあると思います。
「寅」の前についている「壬(みずのえ)」の部分が、十干(じっかん)になるのです。
同じように考えると、2024年は、「甲辰(きのえのたつ)」となりますので、「甲(きのえ)」の部分が十干(じっかん)ということ。
この十干(じっかん)によって、恵方が決まるということが基本なのですが、西暦でわかるなら、西暦で考えた方が、わかりやすいという利点があります。
このことからわかるように、恵方とは毎年違う方角になるように思いがちですが、実は4つの方角しかないということがわかるのです。
2025年は下一桁が5なので、「西南西」が恵方になります。
節分は旧暦でいうお正月の時期

節分は、旧暦でいうと年が切り替わる節目だとされています。
現在では、お正月は1月1日ですが、旧暦では春分の頃がお正月になるのです。
二十四節気では春分の日が春の訪れとして、考えられていますので、一年の始まりだとされているということ。
中国や台湾などアジアの国では、旧暦のお正月をお祝いする風習が残っていますが、日本では旧暦のお正月をお祝いする文化は根付いていません。
その代わりに日本にあるのが、節分という行事だといえるのです。
そのため節分には、旧暦のお正月の名残りも垣間見える風習があります。
正月に寿司を食べる文化から派生している説

恵方巻を食べる文化は、お正月にお寿司を食べていたことから派生して出来たのではないか、とも言われています。
日本では、昔から節目やおめでたい席では、お寿司を食べることが風習とされてきた背景があるのです。
現在でも、お祝いごとの席にはお寿司を用意したりするのも、その風習からきているといえます。
節分は、旧暦では年の変わる大きな節目だったので、恵方巻はこのお寿司を食べる風習と結びついたのではないか、という説です。
北海道では、お正月にお寿司を食べるという文化が色濃く残っている地域もありますので、昔の伝統が受け継がれてきているといえます。
大阪の「丸かぶり寿司」が「恵方巻」になった

恵方巻は大阪にあった風習の「丸かぶり寿司」がもとになっているとされていますが、これは昔から一部の地域にあった風習です。
この風習を大阪の海苔屋さんとお寿司屋さんが、節分に食べることが縁起がいいと結び付けたことでじわじわと関西から西日本に広がっていき、コンビニエンスストアのセブンイレブンが季節の商品として売りはじめました。
その後、ほかのコンビニエンスストアへと取り扱いが広がっていったのですが、この時の名前は「丸かぶり寿司」や「幸運巻き」などといって統一性はなかったのですが、セブンイレブンが「恵方巻」と名付け、全国販売したことが、現在の恵方巻になっています。
その年の恵方に向かって事を行えば何でも吉となり、ご利益が得られる

恵方に向かって恵方巻を食べるのは、多く人が知っていることですが、恵方は節分にだけに関係していることではないのです。
恵方はその年に「歳徳神(としとくじん)」がいる方向なので、その年に恵方を向いて行うことに関しては、何でも吉となるといわれています。
昔の人は、その年の恵方にある神社にお参りをしたり、物事を始めて行う時は、恵方に向かって行っていました。
このように、恵方とはといても身近なものだったのです。
しかし現代では、節分の時にしか恵方を気にすることがなくなってきていて、あまり知られていないといえます。
ところが現代においても、恵方はその年の吉方になるということは変わりありませんので、私たちの生活に取り入れていくことで、ご利益が得られるのです。
「恵方をどう取り入れたらいいのかわからない…」という人も多いかもしれません。
例えば引っ越しを考えている人は、恵方にある物件を探したり、仕事の取引に恵方の方角にある会社をターゲットにしてみる、神社にお参りに行くなら恵方の方角にある神社にお参りするなどといったようなことに、恵方を使ってみてください。
「どこかに出かけたいな…」と思った時も、恵方の方角に向けて出発するなど、事あるごとに恵方に向かって行えばいいのです。
節分だけでなく、日常に恵方を取り入れて生活してみるのも、「歳徳神(としとくじん)」のご利益が得られるチャンスだといえます。
恵方巻のお作法は黙って食べること!
その年の恵方に向かって、黙って食べ切るのは福を取り込むため

恵方巻を食べる時には、いくつかのお作法があります。
誰もが知っている「恵方巻はその年の恵方に向かって、黙って食べ切る」というお作法。
実際に恵方巻を食べている間にずっと黙っているのは、難しいものでついついおしゃべりをしてしまった、なんて人も少なくないものです。
とはいえども、この「恵方に向かって、黙って食べ切る」といわれているのには、きちんとした理由があります。
その年の福を司る神様である「歳徳神(としとくじん)」がいる方向である恵方は、縁起がいいと言われている方角です。
恵方を向いて食べるということは、ご利益を得ることが出来るとされています。
恵方巻を食べる時は、願いを込めながら食べますので、食べている最中におしゃべりをすることは、お願いをしている「歳徳神(としとくじん)」に対して、失礼になるのです。
また恵方を向いて食べることで得られるご利益、福を身体に取り入れている時に、おしゃべりをしてしまうと、せっかく取り入れた福が口から逃げていってしまうとされています。
恵方巻を食べている間は、「歳徳神(としとくじん)」に願いを込めて、黙って食べ切ることで、福を取り込み、ご利益を得られ、願いが叶うといわれているのです。
なぜ恵方に向かって黙って食べ切らなければいけないのか、理由がわかるとなるほどと納得できます。
来年の節分には、正しいお作法で食べることを意識してみましょう。
「笑いながら食べる」という地域もあり、「五行思想」からきている

恵方巻は、「恵方を向いて黙って食べ切ること」というのが、一般的なお作法として知られていますが、地域によっては全く逆の、「笑いながら食べる」とされているところがあります。
「笑う門には福来る」という言葉があるように、笑うことで鬼を追い払い、福を呼び込むという意味からきているのです。
またこの考えの根本には「五行思想」という考え方があります。
「五行思想」という考え方は、「万物は、木・火・土・金・水の5つの要素から成り立っている」というもの。
陰陽道からきているこの「五行思想」は、季節や臓器、色や声の種類、器官などさまざまなことを五行に当てはめています。
この考えでは、春は「木気」にあたり、これを邪魔するとされているのが「金気」になります。
「金気」に勝つのは、「火気」とされていて、この「火気」に属している「笑い」が必要だと考えられるのです。
このようなことから、季節の変わり目で春を迎える節目となる「節分」に笑うことが、邪気を追い払うことに繋がるため、恵方巻を笑いながら食べることが良しとされているといえます。
笑いながら食べることと、無言で食べること、どちらが正解とはいえませんが、どちらも由来や理由としてはきちんとしたものがあるのです。
恵方巻を食べる時は、「目をつぶって食べなければいけない」という決まりごとはない

恵方巻の食べ方として、「目をつぶった方がいいのか?」という疑問を持っている人も少なくありません。
一般的に「目をつぶらなくてはいけない」というルールは、決まっていません。
実際に恵方巻を食べる時に、目をつぶって食べるという人もいれば、目を開けたまま食べている人もいるなど、人によってさまざまだといえます。
恵方巻を食べている間に、願い事をするといった意味で考えれば、目をつぶって食べるというのは理に適っていることだともいえるもの。
神社にお参りに行って神様にお願いごとをする時も、手を合わせたら目をつぶってお願いごとをしますし、神社ではなくても、祈る時は目をつぶるのが、願いごとをする時のスタイルとして浸透しています。
しかし恵方巻を食べる時は、「黙って食べ切る」というお作法がある中、食べ終わるまでずっと目をつぶって食べるというのは、正直難しいことでもあるといえるのです。
目をつぶるというのは、決まりごとではありませんので、各々好きなようにしてもいいといえます。
地域やご家庭のルールとして、目をつぶって食べると決まっているのであれば従うなど、ケースバイケースで変えていっても問題はありません。
「歳徳神(としとくじん)」にお願いをするという、気持ちの持ち方の方が大事なのです。
一人一本の太巻きを用意して、切り分けずに食べ切りましょう

恵方巻は、太巻きを一人につき一本丸々用意するのが、お作法です。
太巻きであるということには、「福を巻き込む」という意味も込められています。
また一本の太巻きは、鬼が持っている「金棒」に見立てられていて、太巻きを「一本丸々」食べ切ることで、鬼退治の意味も含まれているのです。
一本の太巻きを切ることなく食べるというのは、「福との縁を断ち切らない」という意味があります。
一人一本丸ごと食べるということは、「福との縁を切らずに、一人一人が福をしっかりと掴むことが出来るように」という願いが込められているということなのです。
とはいえ、小さなお子様や、ご高齢の方など、長い太巻きを丸々一本食べることが難しい場合もあります。
そんな時は短めのサイズの恵方巻にしたり、細めの恵方巻を準備して、最後まで食べ切れるようにしましょう。
昔は各家庭で作られていた恵方巻ですが、現在では恵方巻を家で作るご家庭も最近では少なくなってきています。
自宅で作る場合は、長さや太さの調節もしやすいものです。
具材も好きなもので作ることが出来ますので、家庭でオリジナルの恵方巻を作って食べるのもおすすめ。
お店で購入する場合も、ハーフサイズの恵方巻など、お店によってサイズも具材も、種類はさまざまありますので、好みのもので、食べ切れるサイズを選んで購入しましょう。
恵方巻を作ってみたい!おすすめの巻き寿司レシピ
代表的な具材は7種類で、七福神にちなんでいる

恵方巻に使われる具材は、7種類の具材とされています。
なぜ7種類かというと、七福神に由来しているといわれているのです。
七福神には、「えびす様」「大黒天様」「毘沙門天様」「弁財天様」「福禄寿様」「寿老人様」「布袋様」がいて、それぞれが福をもたらす神様とされています。
もともと「商売繁盛」や「無病息災」を願って始まったとされている恵方巻なので、七福神にちなんで7種類の具を巻くことが、「福を巻き込む」という意味に繋がっているのです。
7種類というのも、これといって決まっている具材があるわけではありませんが、ベーシックに使われている具材には、「かんぴょう」「伊達巻き」「きゅうり」「高野豆腐」「シイタケ煮」「ウナギ」「桜でんぶ」が多いもの。
現在では、オーソドックスな恵方巻だけではなく、お肉系の恵方巻や、海鮮系の恵方巻、サラダ系の恵方巻などや、なかにはデザート系の恵方巻も売られていたりするなど、いろいろな種類の恵方巻が売られています。
また、具材自体を鬼に見立てて、食べることで鬼退治をするという意味になるものもあるのです。
7種類のベーシックな具材でいえば、「桜でんぶ」が「赤鬼」を表し、「きゅうり」が「青鬼」を表しています。
ほかの具材でも、これは再現できますので、例えば「赤鬼」は海老やトマト、ニンジン、紅ショウガなどの赤いもの、「青鬼」は三つ葉やカイワレ大根、ほうれん草、ネギなどの緑のもの。
オリジナルの組み合わせで作ってもいいので、作ってみてもいいものです。
家で作る時のおすすめの具材や味付け

オーソドックスな7種類の具が入った恵方巻もいいですが、自分でオリジナルの恵方巻も作ってみたいもの。
いくつかおすすめの具材を紹介していきます。
子どもから大人まで好きな人が多い「海鮮系恵方巻」。
海老やサーモン、ホタテ、イカをメインにして大葉と卵焼き、玉ねぎのスライスを巻いて、マヨネーズで味付けをしたものは、年齢問わず食べることが出来ます。
アナゴ、数の子、シイタケ煮、カイワレ大根、卵焼きを巻いて、大人にピッタリの海鮮恵方巻もおすすめです。
子どもやガッツリ食べたいという人には「お肉系恵方巻」。
唐揚げにサニーレタスと、きゅうり、卵焼きなどを入れてマヨネーズで仕上げたり、甘辛いソースで仕上げたりすれば、お腹もいっぱいになります。
牛肉を甘辛く炊いたものと、糸こんにゃくや玉ねぎなど、すき焼きの具を巻いて作った、すき焼き恵方巻もおすすめ。
子ども向けには、カニカマ・卵焼き・ツナ・ウインナー・コーン・そぼろ・きゅうり・リーフレタスなどをマヨネーズと一緒に巻いたり、ウインナーを使うならケチャップもいいといえます。
「変わりダネ恵方巻」も面白いもので、納豆・明太子・白身魚のフライ・チーズ・ニンニクなどの具材を使ったものもおいしいです。
味付けには、味噌ダレを使ったり、柚子胡椒や天丼のたれなどを使うと、変わった味が楽しめます。
スーパーやコンビニには多くの種類が並び、名店監修寿司もおすすめです

年が明けた頃から、スーパーやコンビニエンスストアでは、恵方巻の予約が始まります。
毎年各店舗では、バラエティーに富んだ恵方巻が販売されていて、どれを購入しようか見比べてしまうほど。
店舗ごとに毎年目玉商品が並びますが、どこの店舗でも人気のあるものといえば、「海鮮系恵方巻」です。
リーズナブルな「海鮮系恵方巻」や、贅沢な具材を使った「高級海鮮恵方巻」など、どこも力を入れている商品ばかり。
サイズも太巻き一本のものや、ハーフサイズなど多くの人に対応しているのです。
店舗によっては、有名店とコラボした名店監修の恵方巻も、販売されています。
名店監修のコラボ恵方巻は、数に限りがあって、大人気商品なので、予約が開始されてすぐに売り切れてしまう場合もありますので、予約開始前からチェックしておくのがおすすめです。
恵方巻だけではなく、「節分そば」や「節分ロールケーキ」や「オードブル」まで販売されています。
なかにはペット用の恵方巻を取り扱っているところもあり、各店の節分商戦も激化しているのです。
恵方巻をランチやディナーに!併せて食べたいおすすめの行事食
江戸時代には全国的に食べられていた「節分そば」は縁起物

節分にそばを食べる地域もあります。
出雲そばで有名な出雲地方、山陰や関東の地域でも昔の名残から、そばを食べる風習が残っているのです。
これは「節分そば」と呼ばれる風習で、江戸時代の頃には全国的に広まっていたとされていました。
節分のそばは、縁起物として考えられていて、「健康招福」「無病息災」を願って食べられていたもの。
「そばのように細く長く生きる」というのを聞いたことがある人は、少なくないもので、節分でなくとも縁起物として登場することの多いそば。
また大晦日に一年の締めくくりとして、年越しそばを食べるのは、多くの人が知っていることですが、旧暦で考えると節分は年越しと考えられる日でもあります。
そういった意味で捉えれば、節分にそばという風習も理に適っているといえるのです。
一時は全国的な広がりを見せていた「節分そば」の風習ですが、受け継がれている地域は現在となっては一部の地域だけになってしまいました。
しかし近年のコンビニやスーパーの節分の恵方巻と同じように、「節分そば」が並んでいるところも増えてきましたので、今後改めての広がりが期待できます。
鰯を食べる風習は「柊鰯(ひいらぎいわし)」

広い地域で、節分に鰯の焼き魚を食べる風習があります。
「柊鰯(ひいらぎいわし)」といって、柊の小枝と焼いた鰯の頭を門に飾るというもの。
これは魔除けとして行われていることで、鬼を追い払うという意味があるのです。
節分で鬼を追い払うといえば、豆まきですが、鬼が苦手なものは豆だけではないとされており、その一つが鰯とされています。
もともと門に飾る風習があった鰯ですが、臭いや衛生的な観点から、次第に鰯を食べる風習へと変わっていったとされているのです。
この風習が残っている地域では、節分には鰯の焼き魚を食べたり、鰯の梅煮や鰯の南蛮漬けを食べたりします。
鰯の食べ方に決まったものはありませんので、好きな食べ方で食べてもOK。
昔からよく捕れていたとされている鰯ですが、栄養もたくさんありますので、昔の人にとって鰯は健康を守るために重宝されていた食べ物です。
鰯には「陰の気を消す」という意味があるといわれていることからも、節分に鰯が食べられるようになった理由の一つといえます。
豆まきの大豆が残ったら、大人も子どももうれしい「ちりめん大豆」

節分で豆まきに使った大豆、毎年「残ってしまってどうしよう…」と思っている人も少なくありません。
豆まきに使う大豆は、炒ってあるだけで、味がついているわけではありませんので、アレンジして料理に使うことが出来ます。
たくさん残ったとしても、少しだけだとしても、さまざまな料理に変えて消費することが出来るのです。
その用途は多岐にわたり、福茶や豆ごはんなどの料理、お菓子作りやきな粉に変えるなど、幅広く使えます。
「せっかくなら子どもから大人まで、みんなが食べることが出来て、健康的なものが作りたい!」と思う人も多いもので、そんな時におすすめなのが、「ちりめん大豆」です。
残った大豆の量に合わせてちりめんじゃこを用意し、どちらもフライパンで乾煎りします。
フライパンで砂糖・醤油・みりんを煮詰めて、泡が粘ってきたら、乾煎りした大豆とちりめんじゃこを入れて煮絡めるだけ。
大豆には良質のたんぱく質があり、ちりめんじゃこにはカルシウムが豊富に含まれていますので、栄養面はうれしい限りです。
またちりめん大豆は、学校の給食にもカミカミ献立メニューとして出ることもあり、歯やあごの健康にもうれしい一品。
大人も懐かしい想いがあったり、シンプルに誰もが好きな味でもあります。
そして意外とお酒のおつまみとしても、合うのがちりめん大豆なのです。
豆まきの大豆が残った時には、ちりめん大豆を作ってみてください。
関東の節分は「けんちん汁」で身体を温める

関東の一部の地域では、節分にけんちん汁を食べるという風習があります。
けんちん汁というのは、節分に限らず、ほかの地域でも食べられることがあるので、知っている人も多いものですが、大根・ニンジン・ゴボウ・里芋などの根菜類と、こんにゃくや豆腐をごま油で炒めたあと、出汁を加えて醤油や塩で味付けをして煮込んだもの。
特に寒い地域や、寒い時期の行事ではよく見かけるけんちん汁ですが、身体を温めるためには最適な料理とされています。
身体が温まるといわれるのは、もちろん暖かい汁物だからという理由もありますが、けんちん汁に含まれている油分に、身体を温めてくれる効果があるのです。
けんちん汁の由来としては、鎌倉にある建長寺(けんちょうじ)の僧侶が、崩れたお豆腐を知るものに使ったことから、お寺の名前を取って「建長汁(けんちょうじる)」と呼んでいたものがなまって、けんちん汁と呼ばれるようになったという説が一つ。
また中国から伝わったとされる肉や魚を使っていない「巻繊(ケンチェン)」という料理がなまったという説もあります。
寒い時期に行われる行事にはよく出るけんちん汁が、関東では節分の料理としても食べられていますが、節分の時期はどこも寒さが厳しいので、お家でけんちん汁を作って、身体を温めるのもいいものです。
山口県は節分には「クジラ料理」を食べる

山口県の節分といえば、クジラ料理を食べるという風習があります。
なぜクジラ料理を食べるのかというと、「大きいものを食べると縁起がいい」と言い伝えられていることからきているのです。
節分は一年の節目にもなっていますので、その大きな節目にクジラを食べるということは、「大きな幸せ」を願い、子どもが「大きく元気な子に成長してほしい」という気持ちや、「心や志を大きく持つ」という意味が込められています。
クジラの身体はとても大きく、願いをそのクジラの大きさにあやかって願うといった風習なのです。
現在では捕鯨についての話題もいろいろと挙がっていますが、昔は捕鯨地として栄えていた長門や下関があったことから、山口県ではクジラ料理が伝統的なものとして、郷土料理にもなっています。
家庭料理や、学校の給食にもクジラ料理がよく出てくるなど、山口県の人にとっては身近な食材だったクジラ。
現在でもスーパーで売られたりもしていますが、希少価値が高くなってきたことから、値段も跳ね上がり、日常的には家庭の食卓に出てくることも少なくなってきているといえます。
とはいえ、節分の日には節分コーナーにクジラの肉や、クジラの加工食品である、クジラの竜田揚げやクジラカツ、クジラの味噌煮やクジラベーコンなどが並ぶなどして、現在でも「節分にはクジラ料理」が定着しているといえるのです。
占い師 RINのワンポイントアドバイス「恵方巻は願いごとを祈りながら食べる行事食」

現在では全国に広がっている恵方巻も、実はまだまだ歴史が浅いといえます。
しかしスーパーやコンビニエンスストアなどで、毎年さまざまな恵方巻が販売され、身近な行事です。
恵方巻の正しい作法を知って食べることで、「歳徳神(としとくじん)」のご利益をいただきましょう。























































































 無料占いのmicane(ミカネ)は占いの力でアナタの人生の不安や悩みを無くしてHappyにするフォーチュンメディアです。
占い師やスピリチュアルライターによるコラムも合わせてご覧ください!
無料占いのmicane(ミカネ)は占いの力でアナタの人生の不安や悩みを無くしてHappyにするフォーチュンメディアです。
占い師やスピリチュアルライターによるコラムも合わせてご覧ください!