
季節の暦の読み方に二十四節気というものがあります。
それは、七十二候をより大きく区分している暦です。
季節の流れを感じるだけでなく、立冬など占いにもかかわる暦の1つなので覚えていて損はないでしょう。
二十四節気は、日本の風土や気候に合わせた暦なので季節の旬を感じることができます。
その二十四節気の白露 (はくろ)は、秋が急速に深まっていく時期を指します。空の様子が夏から一気に秋へと進んでいくでしょう。
大気が冷えて、露を結ぶ頃となります。赤とんぼも羽を震わせて飛んでいくでしょう。赤とんぼを見ると秋らしさを感じる人も多いですよね。
目次
白露 (はくろ)の意味や由来
 白露 (はくろ)は、秋であることをはっきりと感じることができる暦です。9月は重陽の節句と言い、長寿を祈る日があります。
白露 (はくろ)は、秋であることをはっきりと感じることができる暦です。9月は重陽の節句と言い、長寿を祈る日があります。
昔は旧暦で暦を数えていたのでちょうど菊の花盛りの時期でした。現代は少し菊が早い時期でもありますが、平安時代は菊の花を鑑賞したりしていました。
盃のお酒に菊の花を浮かべたりと風習に楽しんでいたことが想像できます。花をお酒に浮かべるなんてゆったりとしていて良いですよね。
また、長寿を祝うだけでなく収穫祭の意味あいも持ちます。秋らしい行事であるとも言えます。
そして、秋と言えば収穫の季節ですよね。春からずっと栽培してきて植物たちが実りを迎える時期でもあります。
その植物たちの実りを得たことに感謝をする行事も多いです。今年の収穫を祝うとともに栗ご飯を炊いたりして感謝をしたとも言われていますよ。
また、つばめが南の方へと帰ったりと少しずつ生き物たちにも変化が表れていきます。冬眠にはまだまだ早いですが冬ごもりの準備にかかったりもするのでしょう。
鶺鴒という鳥が鳴く始める時期でもあります。チチィチチィと鳴く鳥です。鶺鴒は歩くときに尾を上下にフリながら地面を叩くようにします。
その様子を石叩きと呼ぶこともあります。また、鶺鴒は日本書紀にも登場するくらい昔から日本にいた鳥です。
鶺鴒が尾や首を振る様子を見るのを見て、イザナギとイザナミが結ばれたという伝説があります。
だからこそ、鶺鴒は縁結びの鳥としても知られているでしょう。
鶺鴒は、暦ができた頃は寒くなると本州より南へ飛んでくる鳥でした。でも、現代では昔よりも温かくなったこともあり1年を通じてみることができる鳥です。
恋愛で悩んでいる時は、ふと鶺鴒のことを思い出してみても良いでしょう。恋教え鳥という異名を持っている鳥なのです。
白露 (はくろ)の時期は「9月7日頃」

| 2021年 | 9月7日(火曜日) |
| 2022年 | 9月8日(木曜日) |
| 2023年 | 9月8日(金曜日) |
| 2024年 | 9月7日(土曜日) |
| 2025年 | 9月7日(日曜日) |
| 2026年 | 9月7日(月曜日) |
| 2027年 | 9月8日(水曜日) |
| 2028年 | 9月7日(木曜日) |
| 2029年 | 9月7日(金曜日) |
| 2030年 | 9月7日(土曜日) |
白露 (はくろ)の時期は、秋が深まってくる時期になります。風の雰囲気もガラッと変わり始めるでしょう。
秋風は、古くから色無き風という呼び名があるくらいです。四柱推命などにも用いられている中国から伝わった五行説によると秋の色は白になります。
日本人はその白を色がないという風に解釈をしたようです。また、華やかさがなく少し寂しいような感じの風だから色がないという表現になったという説もあるでしょう。
でも、白より色無きという方が秋の寂寥感を表現することができて良いのかもしれませんね。
また、潮の流れも少しずつ変化していきます。春と秋のお彼岸の頃が最も干満の差が大きいと言われてます。
春とは干潮の時間が真逆になるので潮干狩りはできません。夜中に貝殻を集める訳にはいきませんよね。
夏に比べて人の数が減った海は寂しげです。さらに波の音が響くとより寂しさが強調されてしまうでしょう。
ほかにも遅れ蚊と言って、夏に活動していた蚊ですが秋になると一気に姿をしていきます。でも、そんな蚊も季節外れの個体もいます。
そんな蚊のことを遅れ蚊と呼びます。この時期の蚊は力なく飛んでいることが多いので人々も夏場よりは優しい目で蚊を見ていたようです。
夏場は目の敵にしていた人も多いので不思議ですよね。
遅れ蚊だけでなく、残る蚊、別れ蚊、あぶれ蚊、哀れ蚊などたくさんの異名を持っています。
それだけでも人々の寛容性も垣間見ることができますよね。秋は、恵みの秋ですが少しずつ寒くなっていくこともあり寂し気な一面もある季節です。
白露 (はくろ)のスピリチュアル的な解釈
 白露 (はくろ)は、夏の終わりの時期です。夏と言えば、太陽が高い位置にあり陽の気が充満している時ですよね。
白露 (はくろ)は、夏の終わりの時期です。夏と言えば、太陽が高い位置にあり陽の気が充満している時ですよね。
そして、冬と言えば陰の気が強い時期でもあります。白露は、その間に位置する暦でしょう。
夏から秋へと季節が進み、ちょうど陰陽が半分くらいのタイミングです。でも、うるさいところから静かなところへと進む方が寂しく感じるのと同じで陰の気を強く感じるかもしれません。
だから、より寂しさを感じるでしょう。ほかにもこのタイミングは十五夜があるタイミングでもあります。
月の美しさを眺めるとどこか異世界へと飛んでいくことができるような気がしませんか?月は昔から人を惑わせてきたとも言われていますよね。
だからこそ、今の自分でないどこかへと飛んでいくことができそうに思えたのでしょう。月というものは何年経っても美しさが変わりません。
今、見ている月も平安時代の人が楽しんでいた月も同じ月なのかもしれませんね。そう考えると浪漫に溢れているとも言えるでしょう。
夏から秋へと季節が進むと寂しさと同時に少し鬱っぽくなってしまう人も少なくありません。
夜が長くなってくると考え込むことも増える上に活動量も減ってくるはずです。だから、少し暗くなるのも自然な変化でしょう。
秋は、実りの季節でもあります。野菜やお米などの美味しい食べ物を食べて体力をつける必要もあるでしょう。
それによって、自身の力をつけて寒く厳しい季節へと対応していくことができるようにしましょう。
なるべく誰かと過ごす時間を増やして、孤独感を最小限に抑える方が良いかもしれませんね。
白露 (はくろ)の旬の野菜は「とんぶり」

「とんぶり」の基本情報
| 栄養 | とんぶりにはビタミンE、ビタミンK、リン、鉄、食物繊維です。血行をよくして冷え性を解消する効果があります。 |
| 選び方 | とんぶりは、生よりも真空パックで流通されていることの方が多いです。長期保存をすることもできるので、真空パックの方が使いやすいと思います。 |
| 保存方法 | とんぶりは、生のものは冷蔵庫で保存します。冷凍することも可能です。真空パックや瓶詰の方が日持ちはするので長期で保存やストックしておきたい場合はそちらの方が良いでしょう。 |
| その他、お役立ち情報 | とんぶりは、淡泊な味なので味付けをする必要があります。醤油やドレッシングなどがよく合いますが時間が経つと粒の中の水分が出て特有のプチプチ感が減ってしまうので味付けは食べる直前に行いましょう。 |
「とんぶり」の特徴
とんぶりは、秋田県の名産品です。畑のキャビアと呼ばれておりプチプチとした食感が美味しいと楽しまれています。見た目は鳥の餌のように見えます。
「とんぶり」のおすすめの食べ方・調理法
とんぶりは、酢の物や大根おろし、長芋などに加えて食感を食べる野菜です。どんぶりなどにのせて食べると美味しいと言われていますよ。
またクックパッドの「とんぶり」に関連するレシピも参考になるので是非ご覧ください。
白露 (はくろ)の旬の魚介類は「カツオ」

「カツオ」の基本情報
| 栄養 | カツオは、タンパク質、EPA、DHA 、ビタミンBなどが含まれています。実が赤いのはミオグロビンという色素です。 |
| 選び方 | カツオは、腹側に黒い縞模様があるものを選びましょう。切り身の場合は、色が深く澄みきった赤色をしているものが良いでしょう。茶色っぽいものはそんなに美味しくないと言えます。 |
| 保存方法 | カツオはアミノ酸のヒスチジンが多いということもあり時間が経つとヒスタミンに変化しアレルギー反応を起こすことが多いので刺身は早く食べるようにしてください。加熱料理用の切り身をラップでぴっちり包んでから冷凍をしましょう。 |
| その他、お役立ち情報 | この時期のカツオは戻りカツオです。戻りガツオは春のカツオに比べて脂が多いカツオです。 |
「カツオ」の特徴
カツオの旬は夏と冬です。それぞれ、脂の量が違い調理法も違うので注意しましょう。関東の市場では1月から秋までと長い期間出回っていますが冷凍ものも多くなっています。日本では、宮崎、三重、静岡、東京、宮城などが主な漁獲地です。
「カツオ」のおすすめの食べ方・調理法
秋の戻りガツオは皮を惹かないと食べることができません。脂が多いので刺身にして食べると良いでしょう。カツオは足が速いので刺身として食べることができるものは新鮮なものだけです。新鮮でないものは塩ゆでにして表面を乾かして「なまり」にしても美味しく食べることができます。
またクックパッドの「カツオ」に関連するレシピも参考になるので是非ご覧ください。
白露 (はくろ)の旬の草花は「シュウメイギク」
.jpg)
「シュウメイギク」の基本情報
| 学名 | シュウメイギク |
| 科・属 | キンボウゲ科 |
| 原産国 | 中国 |
| 別名 | ギブネギク |
「シュウメイギク」の特徴
シュウメイギクは、京都の貴船エリアにたくさん生えていたと言われています。名前が菊なので菊の仲間のようですがアネモネの仲間なのです。
そして、不思議と原産国が中国なのですが英語ではジャパニーズアネモネという名前がついています。
大昔に日本に入ってきたこともあり、人里近い林などに野生化しているものも多くみられています。
秋明菊と各ことが多いですが、秋冥菊と書くこともあります。漢字の印象だけであると正反対になっていますよね。
明るいを適していると考えた人は青い空にピッタリな花であると思ったのでしょう。逆に冥の字を使った人は秋のもの悲しい雰囲気も感じたのかもしれませんね。
どちらも秋らしい様子を醸し出していることもあり、この季節にぴったりな名前であるとも言えるでしょう。
花の姿は日本人が菊と聞いて想像する姿とは少し違っています。見た目はアネモネに似ており、ころんとしたつぼみから薄いピンク色や白の優しい花が開きます。
この花が庭に咲くと秋の風情が漂ってきます。秋らしい雰囲気作りには欠かすことができないでしょう。
茶花として利用されることも多い花です。暑さにも湿度にも強い花なので家庭でも育てやすいと言えるでしょう。
ただし、直射日光に弱いので夏場などは日光を避けるようにしてください。土壌は、弱酸性を好みます。
アルカリ性に傾くと急に育ちが悪くなってしまうので注意してください。
可愛い花なので自宅の庭に植えられていても素敵だと思います。
「シュウメイギク」の花言葉
シュウメイギクの花言葉は、「忍耐」です。シュウメイギクの花の様子は淡く美しい色で小さくて可愛い花です。
その様子がけなげに何かに耐えているように見えているのかもしれませんね。はかなげな花は、秋の風情を映し出しているかのようです。
秋は夏よりは気候として落ち着いているとも言えます。けど、それ以外で我慢が必要なこともあるでしょう。
また、上手く作物を収穫できなければ後1年悩むことになってしまいます。そう考えると忍耐という花言葉はそこまで変ではないと言えますよね。
また、秋の少し鬱々とした気持ちも耐えるしかない場合もあります。耐えるということは辛いことでもありますよね。
耐えることばかりが美徳とは言えませんが、やはり耐えなければならないときは耐えることが大切です。
人々が何かに耐えている時に元気を与えてくれる花でもあるのかもしれませんね。可愛い花の姿を見ていると何となく心が癒されていくはずです。
白露 (はくろ)の七十二候
白露 (はくろ)の初候「玄鳥去(つばめさる)」

白露 (はくろ)の次候「雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)」

白露 (はくろ)の末候「蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)」

時候の挨拶: 白露 (はくろ)の候の使用例
 白露の時期は、栗の花、太陽が眩しい季節などという言葉を使うことが多いでしょう。この時期は、時候の挨拶において「白露の候」を使用します。
白露の時期は、栗の花、太陽が眩しい季節などという言葉を使うことが多いでしょう。この時期は、時候の挨拶において「白露の候」を使用します。
他の二十四節気の意味や時期の一覧
占い師秋桜のワンポイントアドバイス「自分をしっかり持つ!」

ちょっと落ち着いた雰囲気になってしまうからこそ、急に元気を失ってしまう人も少なくないわよ。
秋も収穫祭やお月見みたいなお祭りもあるけど、しんみりと楽しむお祭りだったりもするわよね。
そして、夜が長くなると自分と向き合う時間も増えてしまうわ。けど、その場合も自分をしっかりと持つことが大切よ。
鬱々としてもその鬱に引っ張られない強さがあれば大丈夫よ。強く居続けるということは難しいことかもしれないわ。
だけど、あなたにはそれができるはずよ。



























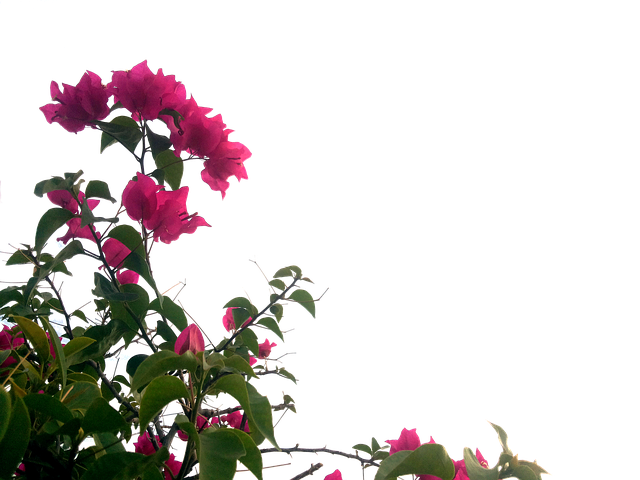






























































 無料占いのmicane(ミカネ)は占いの力でアナタの人生の不安や悩みを無くしてHappyにするフォーチュンメディアです。
占い師やスピリチュアルライターによるコラムも合わせてご覧ください!
無料占いのmicane(ミカネ)は占いの力でアナタの人生の不安や悩みを無くしてHappyにするフォーチュンメディアです。
占い師やスピリチュアルライターによるコラムも合わせてご覧ください!