
皆で一致団結して盛り上がる運動会!
学校や職場、地域などでぜひ開催したい行事の一つですよね。
しかし、参加するだけなら楽しい運動会も、企画運営するとなると話は別。
「どんな運動会にしよう…」と迷ってしまうことも多いでしょう。
そこで、この記事では運動会の目的から注意点、プログラムに加えておきたい種目や盛り上がるBGM、プログラムに添えるイラストなどについて解説していきます。
基本的なことだけでなく、今時のオンライン運動会や老若男女が楽しめる種目についてもご紹介していきます。
この記事を参考に、運動会の企画・運営を成功させていきましょう。
目次
運動会はどうして毎年行うの?意味や歴史を知っておこう
運動会を行う意味とは?運動会は交流を生む

現代を生きる私たちにとって、運動会という行事があるのは当たり前のことです。
どうして行われるのか、その意味を考えたことがある人は少ないのではないでしょうか。
学校で運動会が毎年行われるのには、しっかりとした意味があります。
学校ではさまざまな勉強が行われます。
国語や算数、プログラミングなど現代の学校で学ぶことは多岐にわたっているでしょう。
実は運動会もその学習の一環として行われているのです。
「運動をするだけなら体育の授業だけで十分では?」と考える人もいるかもしれません。
ですが、実際に運動会を行う時のことを考えてみましょう。
運動会は運動会当日だけではなく、準備から子供たちが関わります。
行う種目を決めたり、色分けを考え団長を決めたり、また実際に練習を行う中でどうすればいい得点が取れるのかを考えたりします。
これらは立派な学習であり、子供たちの成長へと繋がるものです。
集団となって勝利を目指す、円滑な運動会運営のため裏方として働く。
運動会を行うことは、単なる娯楽ではなく子供たちの学習へと繋がります。
また、運動会は学び以外にも交流を生み出すものです。
学校で行われる運動会であれば、他の学年と交流することになるでしょう。
地域の運動会は、いろいろな世代との交流が生まれます。
学校で授業を受けているだけでは得られない貴重な経験が、運動会をすることによって得られるのです。
こうした貴重な学びと交流が運動会をする意味だと言えるでしょう。
運動会はいつ始まった?運動会の歴史

運動会の存在は私たち日本人にとって当たり前のものです。
あるのが普通なため、その歴史を知らないという人は多いのではないでしょうか。
今でこそ当たり前に開催されている運動会ですが、はるか昔から日本にあったわけではありません。
日本で初めての運動会が行われたのは、1874年だと言われています。
つまり、それ以前の日本には運動会はなかったということです。
初めての運動会は東京築地の海軍兵学校で、共闘遊戯会というネーミングで行われました。
これはイギリスで行われていたものを取り入れたものであったそうです。
当時の日本の海軍兵学校では、イギリス海軍式の教育が用いられていました。
そのため、イギリスで行われていたアスレチックスポーツを取り入れた行事が開催されることになったのです。
ここから日本の運動会は広がりを見せていきます。
築地の海軍兵学校で共闘遊戯会が行われた1874年、同じ年に今の北海道大学である札幌農学校で力芸会という名前で運動会が開催されています。
運動会という名前が確認できるのは1885年、東京大学で行われた行事です。
時間をかけて徐々に全国に広がり、1880年代半ばには学校での定番の行事となっていきました。
行われる種目にも歴史と共に変遷があります。
初めての運動会は子供のものというよりも、兵隊の力比べや訓練という意味合いが強いものでした。
その後、学校へと広まった後も、競い合い優劣を決める種目が多くありましたが、近年では優劣をつけないチームワークを評価するようなものが増えてきました。
運動会運営の注意点「事故」「けが」「熱中症」

運動会を企画・運営するなら、楽しいものにすることはもちろんですが、安全な運動会にしなくてはなりません。
いくらたくさんの人が楽しんでくれたとしても、対策の不備でけが人が出るようでは大満足の運動会とは言えなくなってしまいます。
運動会担当になったのなら、そうした面の対策にも気を配っていきましょう。
まずは行う時期です。
通常秋に行われるイメージのある運動会ですが、現在では春に行う学校も増えてきています。
それは秋開催だと練習時期が夏の暑い時期になり、熱中症の危険性があるからです。
さらに秋は残暑も厳しく、開催日にも気温が高いことが考えられます。
春開催にすれば入学・進級直後となり練習期間は短くなってしまいますが、まだ日差しの厳しくない内に練習・本番を行うことができます。
また、運動会をどの季節に行うにしても、避けられないのはけがでしょう。
運動を行う時にはどんなに対策しても、転倒などのけがは起きてしまいます。
競技自体の安全性の確認はもちろん、どうやっても防げないけがのために救護所の設置などを忘れてはいけません。
運動会は安全なものであることが大前提です。
他に運動会で考えられる問題点としては観客をどうするかです。
場所取りは何時から解放するのか、観客は一人につき何人まで許可するのか、テントやタープは許可するのか…。
トラブルが起きないためには、そうしたことを細かに決めておく必要があります。
運営側に回ったのなら、運動会の事故、けが、問題点にまで気を配るようにしていきましょう。
コロナ禍の運動会はオンラインで行われることも、オンライン運動会のやり方

コロナ禍以降、運動会はオンラインで開催されることも多くなりました。
運動会を開催するならオンラインも視野に入れておく必要があるでしょう。
といっても、オンラインでの運動会は経験がないとどうしていいかまったく分からないものです。
オンラインでの運動会の礼は次の通りです。
まず、参加者は自宅からズームなどを利用して参加するため、一つの所に集まることがありません。
感染症への不安がある人も安心して参加することができますね。
「オンラインでの運動会は一致団結が感じられないのでは…」と感じる人もいるかもしれません。
しかし、その心配もオンライン運動会ならではの競技内容で吹き飛ばすことができます。
オンライン運動会で用いられる競技としておすすめなのが、借り物しりとりリレーです。
家にあるものを使ってチームでしりとりを繋いでいき、早く最後の人までたどり着いた方が勝ちというもの。
実際に集まって行う借り物競争よりも、家にあるものを利用するので思ってもみないようなものが出てくる楽しみがあります。
他にもオンラインならではの競技として、ジェスチャーマッチングゲームがあります。
お題に対するジェスチャーを各チーム「せーの」で行い、同じポーズをとっている人が多い
チームの勝ちという競技です。
オンライン運動会のポイントは、オンラインでも勝敗が分かりやすく楽しめることです。
コロナ禍での運動会に対する考え方は人によってさまざまでしょう。
ですが、オンラインなら誰でも安心して参加することができます。
注目のゆるスポーツを運動会にも取り入れよう!

運動会の主役は運動の得意な人になりがちです。
そのようなことを避け、誰もが楽しめる種目として注目されているのがゆるスポーツです。
ゆるスポーツはその名の通り、ゆるいスポーツなので体力のない人でも楽しむことができます。
運動会を企画運営するなら、ゆるスポーツを取り入れることも検討してみてください。
運動会でできそうなおすすめのゆるスポーツはスポーツかるたです。
スポーツかるたは普通のかるたと同じように読み札と取り札があり、読まれたひらがなの札を相手よりも早く取るという点では普通のかるたと変わりません。
しかし、取り札にはお題が書かれており、そのお題を実行することによってポイントが加算されます。
といってもお題は難しいものではなく、公式のスポーツかるたの「あ」の札に書かれているのは「安静にして心拍数を測ってみよう」というものです。
他の札も簡単で誰にでもできるようなものばかり。
公式のかるたを使うのではなく、参加者で札の内容を考えてかるたの作成から行うのもいいですね。
ゆるスポーツはスポーツ弱者をなくすという目的のもと作られたスポーツ。
それを運動会の種目に取り入れることで、スポーツの得意不得意や年齢性別関係なく誰でも楽しめるようになります。
「運動会が苦手だな…」というような人にも楽しんでもらうためには、ゆるスポーツを取り入れることも考えてみましょう。
運動会では必ず行おう、熱中症対策と感染症対策

最近の運動会の対策として欠かせないのが、熱中症と感染症への対策をしっかりと行うことです。
運動会は秋に開催されることが多いでしょう。
「スポーツの秋」と呼ばれるように、秋は運動をするのにちょうどいい気候です。
しかし、それは一昔前の話になりました。
温暖化が進み、残暑も厳しくなった現代において、秋でも熱中症対策は気の抜けないものとなったのです。
また、運動会当日の気温にだけ注意すればいいというものでもありません。
運動会には事前の準備や練習がつきものです。
練習中に熱中症で倒れることがないようにということにまで気を配る必要があるでしょう。
参加者の待機場所にはテントを張って日陰を作る、給水のための時間を十分に取るなど基本的な熱中症対策をしていきましょう。
春に運動会を開催する学校も増えてきたようですが、春だからといって熱中症対策はおろそかにできません。
春開催は年によっては肌寒かったり、夏並みの気温になったりということがありますので注意してください。
そして、コロナ禍以降、運動会のように人が集まる行事に欠かせなくなったのが感染症対策です。
どうしても行事をやれば、人が集まり密になりやすいもの。
そこをどう対策していくかも運営側の腕の見せ所だと言えるでしょう。
運動会の基本的な感染症対策としては、まず観客の人数を制限することです。
開催場所の広さや規模に合わせて、各家庭1人や2人といった具合に観客の人数には制限を設けておきましょう。
人数を絞った上で、観客の出入り口は一つにし手指消毒と検温をします。
さらに声を出さずに見ることのお願いと、間を取って見てもらうように区切りの線を書いておくのもいいでしょう。
選手と観客は場所を分けて、接触のないようにすることも重要です。
もし感染者が出てしまえば、今後の運動会の開催自体が危ぶまれますから念には念を入れた対策が必要となります。
運動会のプログラム編成や種目はどうする?学年&クラス別おすすめ種目
運動会で全学年におすすめ「徒競走」

学年を問わず運動会といえば徒競走は定番の種目でしょう。
ですが、ただ走ればいいというものでもありません。
徒競走をするのなら注意したいのは、いい勝負になるようにすることです。
全員参加の徒競走の場合、走るのが遅い子もいれば早い子もいるでしょう。
あまりにも早さに差があると、参加する子供も見ている大人もつまらなく感じてしまいます。
だから、いい勝負になるようにタイム順に走順を考えていきましょう。
同じような実力の人と走ることで、徒競走はとても面白い競技になります。
徒競走を種目に加えるのなら、走順を検討することは忘れないでおきましょう。
運動会で中学年以上におすすめ「障害物走」

走るコース上に障害物を設けた障害物走も、運動会を盛り上げてくれる種目です。
運動会で障害物走をするのなら注意点は一つ。
それは準備や片づけが簡単なものであることです。
いくら盛り上がる障害を用意しても準備に時間がかかってしまえば、運動会全体の進行を妨げることになってしまいます。
障害物走だけを行うのでなくその前後にも種目はあるので、準備や片づけのことも頭に入れておくようにしましょう。
簡単に準備ができる障害としては、ネットくぐり、じゃんけんに勝ったら進める、平均台の上を通るなどがあります。
ちょっとした障害があるだけでもレースは盛り上がり、運動会が楽しいものとなります。
運動会で全学年におすすめリレー

運動会を盛り上げるためには、リレーは必須の種目でしょう。
リレーは全員が走るものと、選抜選手が走るものの二種類があります。
クラス全員が走るものにする場合、走順を決めるのもぜひ子供にやらせてみてください。
どういう順番で走るかは勝利のために重要な戦略となります。
そういったことを考えるところから、もう勝負は始まっており、良い学びとなります。
選抜リレーは選ばれた人が学年を超えたチームとなり走って競うものです。
選抜リレーは運動会の花形種目で、選ばれなかった子供たちも応援で盛り上がることができるでしょう。
選抜リレーの得点配分を大きくすると、白熱の運動会となること間違いなしです。
選抜メンバーを決める事前のレースから、運動会熱が高まっていきます。
選手を選んだ後は、チームで練習を繰り返すといいでしょう。
運動会で全学年におすすめ「ダンス」「マスゲーム」

全員が一致団結する楽しみを感じてもらうには、ダンスやマスゲームといった種目もおすすめです。
ダンスやマスゲームをするのなら、先生が考えるよりも子供主導にするのがおすすめ。
考えられた動きを合わせるよりも、子供が自分で考えた動きを全員に伝えていく方がいい学習となります。
高学年が中心となりダンスを考えて、それを下級生に指導していきましょう。
子供主導だと時間はかかりますが、達成感や人に指導することの難しさを学んでいくいい機会となります。
大人が手を出すのは子供が本当に困った時だけにして、子供たちの成長を見守っていきましょう。
ダンスやマスゲームを行う場合は、練習時間が多く必要となるので、その時間が確保できるかの検討も忘れないでください。
時間が確保できる場合は、大きな学びの場となりますのでぜひ取り入れたい種目の1つです。
みんなが揃って同じ動きができるようになった時の喜びは、他の種目ではなかなか味わうことのできないものです。
運動会で高学年におすすめ「長縄跳び」

長縄跳びは大縄跳びとも呼ばれる種目で、長い縄を跳べた数を競います。
一人が縄に入って抜けて、またその次の人が入って…。
というようなスタイルと、全員が同時に縄の内側に立ち同時に跳べた回数を競うものとがあります。
どちらにしても、全員での協力が勝利のためには欠かせません。
長縄跳びを行う際に注意しておきたいのが、勝利を目指すあまり失敗した子を責める空気ができてしまわないことです。
理想的なのは、失敗した子にどうやればうまくできるかアドバイスできること。
勝利を目指すのはいいことですが、そのためにみんなで高め合うのだという雰囲気を作っていきましょう。
その雰囲気ができれば、子供たちはみんなで作戦を考え自主的に練習をするようになります。
そうして最善を尽くせば、結果はどうあれ満足できるものとなるでしょう。
長縄跳びが苦手な人はどうしてもいます。
そうした子を責めることなく、みんなで支え合う種目となっていく筋道作りだけは忘れないでください。
運動会で年齢や学年が違っても楽しめるおすすめの団体競技&種目
みんなで協力「鈴割」「玉入れ」

運動会で学年や年齢が違っても楽しめるのは、鈴割や玉入れです。
鈴割は大きな鈴めがけて玉をぶつけ、玉が割れるまでのタイムを競う種目です。
タイムを競わず、ただ鈴が割れるさまを楽しむだけということもあります。
玉入れは高いところにあるカゴに玉を投げ、いくつ玉が入ったかを競うものです。
どちらも玉を投げるという単純な動作で目的が分かりやすく、全学年でできる競技です。
学年を分けず全体でやる場合は、高学年が前を独占してしまい低学年が満足に投げられないことが考えられます。
学年ごとのゾーンを決める、低学年がまず先に投げる、といった対応策を考える必要があるでしょう。
全員が協力して鈴が割れた時、またはかご一杯にたまった玉を見た時。
協力して何かを行うことの素晴らしさを体感できる種目です。
玉入れは競技中だけでなく、玉を数える時も非常に盛り上がります。
「ひとーつ、ふたーつ、みっつ…」
大きく数えながら玉を天高く放り投げる。
いったいいくつ玉が入ったのだろうとワクワクするその瞬間は貴重なものです。
鈴割・玉入れは参加者も観客も盛り上がる種目になるでしょう。
観客も協力して盛り上がる「借り物競争」

借り物競争のやり方は次の通り。
徒競走の途中に伏せられたカードがあり、そのカードをめくると物の名前が書いてあります。
その物を会場の中から探し出し、ゴールまで持ってくるというものです。
カードに書くものは運動会会場にありそうなものにしなければなりません。
また、物だけではなく「校長先生」や「お母さん」など人を書いても大変盛り上がります。
書くのを人に限定すれば借り人競争という、少し変わった種目となります。
コロナ禍では物を探して人をかき分けるようなことは難しいかもしれませんが、感染状況が落ち着いたら運動会には入れたい種目の一つです。
気持ちを一つにして引こう「綱引き」

綱引きは綱を引き合うという単純な競技ながら、勝ち負けが明快でとても盛り上がる競技です。
感染症が心配される中でも、相手チームとの距離、自分のチームも距離が取りやすくおすすめの競技となります。
綱引きは年齢や学年が違っても、チーム全体の力と団結力で戦う種目です。
協力する楽しさや喜びを感じられるでしょう。
また、綱引きは綱一本あればできる競技です。
準備が簡単で盛り上がるという点でも、綱引きは運動会で外せない団体競技です。
全学年でやるのではなく、一学年でやっても盛り上がります。
綱引きは単純そうに見えて、なかなか奥が深い競技です。
並ぶ順番、綱の引き方など、さまざまな作戦を立てて競技に臨めば練習では勝てなかった相手に勝つというような番狂わせも起きてくるでしょう。
息を合わせて走る「でかパン競争」

でかパン競争は、二人組でのレースです。
大きなパンツを用意して、足を通す部分に一人ずつが入ります。
そして、二人でパンツに入ったまま走り、コースを一周してきたらパンツから出て次の二人組にバトンタッチです。
パンツに出たり入ったりという動作が加わることで、単純に足の速さだけでなく協調性が問われるレースとなります。
二人組で走るということは、一人で走るのとは違ってペアと息を合わせる必要があります。
自分が足が速いからといって、先に走ってしまえばパンツでつながっている相手は転んでしまうでしょう。
でかパン競争は、相手のことを思いやる気持ちも育てることができる運動会の種目です。
転ばないように気を付けて「二人三脚」「ムカデ競争」

でかパン競争よりも、より協調性が問われるのが二人三脚とムカデ競争です。
足をひもで縛りつけるので、より自由が奪われ息をピッタリ合わせないと早く進むことはできません。
二人三脚は横並びになった二人の足をしばり、ムカデ競争は縦一列に並んだ人の足をひもでつなぎます。
「せーの」と声をかけ、足を上手に動かさなければ、たちまち転んでしまうでしょう。
リードしていると思っても、少しの乱れで大逆転が起きるのも二人三脚やムカデ競争の面白いところ。
個々の能力の高さよりも、協調性と練習量がものを言う種目。
こうした競技を取り入れることで、運動会は面白いものとなっていきます。
早くそして丁寧に「バケツリレー」

そもそもは防災種目であったバケツリレーですが、運動会で取り入れても盛り上がる種目となります。
バケツリレーのやり方は一列に並んで水の入ったバケツを渡していき、最後の人にたどりつくまでのタイムを競うというものです。
急いでバケツを渡すと水がこぼれ、最後には水があまり残っていないということもあるでしょう。
残った水の量を点数に加味しても面白くなります。
また、水でやると服や靴が濡れてしまい大変であることを考えるなら、バケツに入れるのは水でなくても構いません。
玉入れに使う玉を入れて、こぼれた分は減点するなどしてもいいでしょう。
早く運ばなければならないけれど、慎重さも必要とされる。
ドキドキハラハラの団体競技となるでしょう。
運動会の花形種目「リレー(団体)」

リレーは運動会が盛り上がるためには欠かせない種目です。
団体で行うリレーは、チームの中に早い人もいれば遅い人もいます。
それをどうまとめていくかがリレーという競技の楽しさです。
先頭やアンカーだけでなく、みんなの力でバトンをつないで勝利することを目的に努力する。
運動会当日だけでなく、リレーはその前の準備段階も大切なのです。
練習では強かったチームが本番でも確実に勝つわけではないのが、リレーの面白いところ。
練習も本番も力を出し切り、悔いのないようにすることの大切さを伝えていきましょう。
白熱の戦い「騎馬戦」

騎馬戦は運動会の種目の中でも最も白熱する種目ではないでしょうか。
運動会を行うならぜひ取り入れたい種目の1つではありますが、白熱するだけに注意点もあります。
騎馬戦は騎馬の組み方をしっかりと指導しなければ、とても危ない競技となってしまうでしょう。
さまざまな騎馬の組み方がありますが、最もメジャーなのは土台が3人で上に乗るのが1人のものです。
騎馬戦は崩れてしまうと危ないので、安定していることが何よりも大事となります。
土台の人の背の高さを合わせると安定性は増します。
上に乗る子は相手の帽子を取るときにだけ立ち上がるようにし、移動の時は座っておくようにします。
馬の進む方向が合わなければ落馬の原因となってしまいますので、誰か司令塔を決めておくのも重要です。
運動会が盛り上がる曲!定番BGMとおすすめソング
色ごとに歌おう「運動会の歌 ゴーゴーゴー」
運動会の定番の歌といえば運動会の歌ゴーゴーゴーです。ゴーゴーゴーの特徴は各色の歌詞があるということ。
赤色なら赤色、白色なら白色のための歌詞があるので、自分のチームを応援する歌としても役立ちます。
自分の色を連呼しながらゴーゴーゴーと気分を高めてくれる歌詞は、運動会全体を盛り上げてくれます。
かけっこの定番ソング「クシコスポスト」「道化師のギャロップ」「トランペット吹きの休日」
かけっこの時によく使われるBGMがクシコスポストです。ヘルマンネッケ作曲のもので、運動会に使われているのはあまり原曲には忠実ではないそうです。
道化師のギャロップは、ソビエト連邦を代表するカバレフスキーという作曲家の作った曲。
ギャロップというのは馬術用語で、馬の全速力のことを意味しています。
あのテンポのよさは、馬の走る様子を表しているのですね。
トランペット吹きの休日は、オーケストラで怒られてばかりのトランペット吹きが休日に自由に吹くというイメージで作られた曲だそうです。
この曲もかけっこの時によく使われる、盛り上がるBGMの1つでしょう。
クシコスポスト、道化師のギャロップ、トランペット吹きの休日の3つともタイトルは聞いたことがなかったかもしれませんが、曲を聴けば誰もが聞いたことのある運動会ソングなはずです。
入場曲におすすめ「2億4千万の瞳」「ハピネス」
運動会は入場のシーンも大切です。入場の気分を高めれば、運動会の成功も確かなものとなるでしょう。
そんな時のBGMにぴったりなのが見ている人の気持ちも高めてくれるものです。
幅広い世代に知られており楽しい曲といえば、郷ひろみの2億4千万の瞳と嵐のハピネスです。
駆け足で入場してくる子供たちのテンポにもぴったりで、楽しい運動会の期待を高めてくれます。
種目のBGMに「勇気100%」「天国と地獄」「嵐」「世界に一つだけの花」
運動会の種目でのBGMもやはり知名度とテンポが合ったものがおすすめです。勇気100%は発売は1993年ですが、代々歌い継がれて忍たま乱太郎の主題歌となっており、パパママ世代から子供たちにまで広く知られた歌です。
オッフェンバックが作曲した天国と地獄は、運動会のハラハラドキドキにぴったりで、どこの運動会でもよく用いられています。
嵐や世界に一つだけの花も知名度の点で、運動会を盛り上げてくれるでしょう。
入場行進におすすめの曲「星条旗よ永遠なれ」「威風堂々」「ワシントンポスト」「双頭の鷲の旗の下に」
行進の時の曲は、威厳があって参加者たちがかっこよく見えるような曲がおすすめです。星条旗よ永遠なれはアメリカの海兵隊音楽隊長ジョン・フィリップ・スーザが作った行進曲で、行進のためにある曲と言えるでしょう。
威風堂々もイギリスのエドワード・エルガーによって行進曲として作られており、運動会の行進のシーンにもぴったりです。
ワシントンポストも星条旗よ永遠なれと同じスーザが作った行進曲です。
双頭の鷲の旗の下にはドイツのヨーゼフ・フランツ・ワーグナーが作曲した行進曲。
リズミカルで行進する人も、見ている人もテンションが上がる曲でしょう。
表彰式の歌はこれ!「見よ、勇者は帰る」
表彰式もBGMをつけると盛り上がりが増します。表彰式定番のBGMといえば「見よ、勇者は帰る」です。
勇者が勇ましく帰る様子を描いた曲が表彰される人をよりかっこよく見せてくれます。
誰もが表彰曲といえばこの曲を思い出すでしょう。
見よ、勇者は帰るは表彰式には欠かせない曲なので、用意するのを忘れないでください。
運動会には今年のヒットソングも外せない

運動会を盛り上げてくれるのは、例年流れる定番曲だけではありません。
その年のヒットソングもBGMとしてぴったりです。
流行っている曲は気分を乗せてくれますし、動画を撮って後で見返した時にも懐かしく感じることができます。
BGMに迷った時には、その年のヒットソングをぜひ流してみてください。
流行りのアニメのテーマソングや、最近のヒットチャートの中に、運動会BGMのヒントがあるでしょう。
ただし、バラードは運動会には不向きなので、いくら流行っていても使用は控えた方がいいかもしれません。
アップテンポで楽しくなるような選曲を心掛けてみてください。
運動会のプログラムのイラストはどうする?
小学生以上ならイラストを児童から公募するのもあり

運動会に欠かせないものといえばプログラムです。
参加者だけでなく、観覧者にも配られるプログラムは、子供たちの手で作り上げるのがおすすめ。
児童から公募する形でイラストを描いてもらえば、手作り感が出て温かみのあるプログラムになります。
児童たちも自分たちで作ったという気持ちが増し、プログラムへの愛着が増すでしょう。
児童全員にイラスト応募用紙を配り、提出期限を設け、多数のイラストを募ってみましょう。
クラブや部活ごとにイラストを提出してもらおう

クラブや部活ごとに、プログラムの一部分を担当してもらうのもいいでしょう。
各クラブや部活の色が出て、面白いプログラムが完成するでしょう。
生徒全員からの公募ではやる気が出ない人も、クラブや部活単位となれば参加してくれると考えられます。
自分たちがイラストを出す楽しみだけでなく、他のクラブや部活はどんなイラストを出しているのかという楽しみもあります。
プログラムのイラストに困ったら素材集、イラスト集を使おう
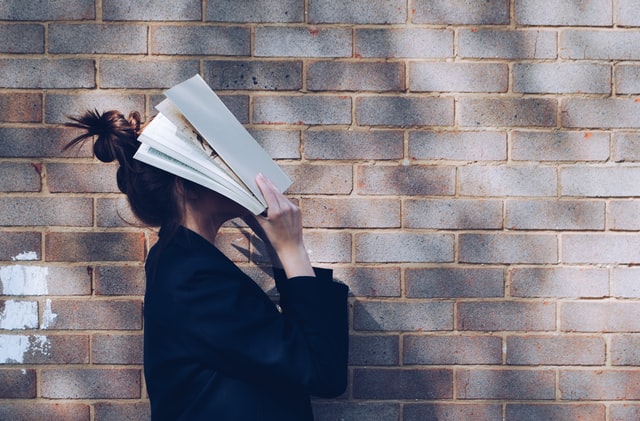
プログラムを華やかにするには、空いている箇所にイラストを載せるのもいいでしょう。
運営側にイラストが描ける人がいないという場合でも大丈夫。
学校にはプログラムに使えそうな素材集やイラスト集があります。
そこから、プログラムに合うイラストを見つけて、プログラムを彩ってみましょう。
プログラムはただ競技の順番が書いてあればいいというものではありません。
運動会の楽しい気持ちを盛り上げてくれるイラストを差し込んで、プログラムをかわいいものにしていきましょう。
ネットのフリー素材サイトのイラストは無料で使える

現代は便利な時代なので、ネット上にフリー素材がたくさんあります。
そうしたものを使ってプログラムを華やかにしていきましょう。
ネットの世界からイラストを探してくれば、毎年同じようなプログラムからの脱却が可能となります。
「いつも同じようなプログラムになってしまっている…」
そんなお悩みを抱えているのなら、ぜひネットからフリー素材を探してみてください。
フリー素材はフリーというだけあって、無料で簡単な会員登録で使えることがほとんどです。
プログラムにイラストを使うなら著作権に注意

自分や子供が描いたイラストを使うのなら、何の問題もなく使用すればいいでしょう。
しかし、他人が描いたイラストを使う時には注意しなければならないことがあります。
それは著作権の問題です。
ネットを見渡せば素敵なイラストはたくさんありますが、それらは誰かの作品であり勝手に使っていいものではありません。
もし勝手にプログラムに使用してしまえば、著作権を侵害していることになるでしょう。
また、芸能人の写真などを載せるのもいけません。
プログラムを作るのにネットを利用する場合は、著作権の問題には気をつけましょう。
フリーだと明記してあるイラストであれば問題はありません。
占い師 小鳥のワンポイントアドバイス「運動会は世代を超えて盛り上がろう」

たくさんの人が集まって一致団結して行う運動会は、私たちの人生の楽しみと言えるでしょう。
そして、せっかく運動会を開催することになったのなら、その運動会を多くの人が盛り上がるものにしたいと思うでしょう。
そのためには、運動会の安全面、種目、BGM、そしてプログラムにまでこだわって準備を進めましょう。
企画運営する側は大変ですが、押さえるべきポイントを押さえて準備すれば、運動会当日は想像以上の盛り上がりを見せるはずです。
感染症対策などで開催が危ぶまれることも多い運動会ですが、開催が可能となったのなら十分に注意し全力で楽しみましょう。
運動会は世代を超えて盛り上がることのできる素敵な行事です。






















































































 無料占いのmicane(ミカネ)は占いの力でアナタの人生の不安や悩みを無くしてHappyにするフォーチュンメディアです。
占い師やスピリチュアルライターによるコラムも合わせてご覧ください!
無料占いのmicane(ミカネ)は占いの力でアナタの人生の不安や悩みを無くしてHappyにするフォーチュンメディアです。
占い師やスピリチュアルライターによるコラムも合わせてご覧ください!